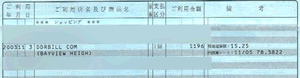|
|
|
|
■複製に対する認識(2005.9.7)
先日、ソースネクスト社がPowerDiscDVD
DoubleLayerの発売をしているのを見た。このソフトウェアは誰でも簡単にDVDメディアがコピーできることを売りにしており、これまでのバックアップを主題にした同様のソフトウェアとはその「目的」がかなり異なるものだ。利用者の声には、レンタルショップで借りたDVDをコピーしてじっくり見ることができて良かったとある。管理人はこれはメディアの著作権違反ではないかと考えた。ご存知であろうか。DVDはCDと違って、商用や二次利用をしない場合であっても、無断で複製してはならないということを。恐らくはDVDメディアの起動画面でそうし注意書きを目にしているはずだ。そこで問い合わせて見たのが、以下である。
(問い合わせ内容の全文)
『当方購入はしていませんが、御社HPの紹介ページに
PowerDiscDVD DoubleLayerの利用者の声として、下記のよ
うな記述がありますが、これは違法ではありませんか。個
人に著作権の帰属するDVD(自作)は本人の複製におい
て認められますが、レンタル会社から供給される製品はす
べて製作会社や製作者に著作権が帰属するもので、複製の
段階で違法行為となります。こうした声をそのまま載せる
という御社の判断に疑問があります。解釈が異なればご教
示ください。
「DVDをコピーできるなんて全く知らなかったのですがこう
いうソフトがあるなんてとっても嬉しいです。DVDを借りて
きてみたくても近くにレンタル店がない為困っていまし
た。でもこれからは出かけた際にレンタルして、車の中で
コピーして観ます。(北海道/宮川 るみ子さん)」』
これに対して、早急にお返事をいただきました。ソースネクスト様ありがとうございます。
だがしかし、DVDメディアのそれぞれに記載のある使用許諾には確かに個人で楽しむ場合においても複製を禁ずる記載があるものがあり、これらを無視できないのではないか。同社の回答の全文を記載する。
(問い合わせ内容の全文)
「お問い合わせいただきました件につき、ご案内いたします。
お客様よりいただきました「お客様の声」を確認いたしましたが、
著作権法第5条で複製権を許されております、「私的使用(個人的に又は
家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること)」
を超えない範囲の使用方法と考えます。
この「私的使用」は、お客様が複製するDVDが、お客様自身が購入した
DVDであるか、レンタルされたDVDであるかを問わずに適用されると
思われます。
以上、よろしくお願いいたします。
今後も弊社並びに弊社製品を何卒よろしくお願い申し上げます。
--- お客様からのお問い合せ内容 ---
■件名:PowerDiscDVD DoubleLayerの使用方法について
(20050814194507010804)」ー
別に物議をかもしたいわけではないが、ソフトウェアを売らんがために解釈をうまくとって消費者の欲望を引き出すことはほめられたものではない。少なくとも利用者の声にある「北海道の宮川るみ子さん」は、今後片っ端からDVDをレンタルするかもしれない。ソフトウェア提供元から利用についての細かい指導があるとは思えないし、例えあっても利用者は関心を寄せないであろう。まして著作権を意識することなどない。家に撮りためたコピーメディアをさらに複製することも簡単であるし、再配布の可能性もないとは言いきれない。利用者のそうした意識改革をソフトウェア提供元がやらずして、著作権云々ということを持ち出して合法を訴え続けるのであれば、映像やソフトウェアの保護は形だけの著作権のために堕落崩壊するであろう。
|
|
|
|
|
■OA管理者の集い(2005.7.13)
うちの会社には十数か所の事業場(工場や支店)がある。それら拠点には各事業場で任命されたOA管理者がいる。場内のOA管理全般と障害発生時の連絡係であるが、それらは業務ではなく、いわばボランティアである。
先日、総勢を本社に集めて、機器管理や保守、セキュリティについて説明会を開いた。社内ではこれに「OA管理者の集い」という、やや古風な名前が冠せられ、3〜4年に一度当方所属する情報部門が主催している。毎回思うことだが、OA管理者はタイプが2つに分かれる。OA管理にまるで無関心なタイプと、逆にマニアックなパソコン好きのタイプの両極端である。ボランティアでやっているから、贅沢は言えないが、中庸が欲しい。OA管理者に求められるものは、普段の地道な『機器管理』と『障害時の迅速な連絡』である。コンピュータの知識は基本以外は何も要らないと常に強調するのだが、事業場から選出されるメンバーはみなパソコン好きである。でなければ、OA管理者任命を逆らえない立場の新人社員などである。
現在、これら軽視されるOA管理者の職制化(部門化)を目指す。各事業場に「OA課」を設置し、OA業務専任となれば、給料を払うわけだから、事業場も安易な人選はしないだろう。社内的にはOA業務そのものへの意識が低く、相当実現は厳しいが。
|
|
|
■情報管理部門って何さ(2005.5.23)
先日、社内の一工場のネットワーク改良を行なった。社内のネットワークを管理する部署に所属する立場上、こうした工事を進めることは当然だし、ときとして思いもよらないトラブルに遭遇し、社内ネットワークを停めてしまうなんてこともある。もちろん管理人はこうした技術的障害への対応は好むわけもないが、それは仕事と割り切って徹夜でも何でもして、復旧に努める。復旧がかなったときの達成感も心地よい。
しかしこのところ、技術障害よりも、人的障害?が多い。一般的に社内において、総務部や秘書室、そして当方の所属する情報室などの管理部門は、製造や営業部門から低く見られている傾向がある。本来ネットワークの管理は利用側の情報提供が欠かせないものである。それはコンピュータをはじめとするネットワーク接続機器の配置は言うまでもなく、機器更新や転勤による利用者の変更等逐次更新情報である。これらは情報部門が調査するのではなく、あくまで利用者側が提供するものと思う。だがそれらを提供せずにトラブルや困ったときだけの責任を追及する傾向がある。今回の改良工事に至った原因も、もとは利用側の情報提供を怠った対応がネットワークトラブルを引き起こしたものと思うが、そんなことはお構いなしである。『動かなくなった。おまえらの責任だ。さっさと直せ!』とばかりの相手の物言いに、さすがに切れた(ていうかよく切れるけど)。
もっともこれは『自分たちのネットワークは自分たちで守る』という意識が欠けていることや、管理部門に対する差別意識というより、基本的な部署間の交流マナーの欠如ともいうべきか。別の部門の上級職が、相手の部署の部員へ上司を通さずに依頼をしてみたりすることも多いし、もはやこれらは自分の会社のモラル低下。このようなことを嘆いているのは一ネットワーク管理者だけではないかもしれない。
|
|
|
|
|
■どちら様ですか?(2005.4.11)
スパムメールの猛威は相変わらずである。これに腹を立てて抗議のメールを返信したりしてはならない。
「送信を止めたい方はこちらにアドレスをどうぞ」的なページにも絶対アドレスを入力しないこと。
スパムメールの摘発機関がいくつかあるから、これらの機関に頼るか、または無視するしかない。
下記のような勧誘メールも増えている。個人名でいかにも遠慮しながら送ってきているような文章は、良心を持った人ならば少なからず、「自分のメールが見ず知らずの人に迷惑をかけている。早く連絡をしなければ」と思わせる。悲しいかな〜@yahoo.co.jpや〜@msn.co.jp等のWEBメールはもう信用できない。これらWEBメールがスパムメールの温床になる理由は、その登録時の匿名性である。ちょうどプリペイド携帯と同じで、でたらめの情報で好きなアドレスで新規登録ができてしまう。
かといって本当に自分のメールが送信者詐称等で迷惑をかけていたらどうしたら良いか。きっと相手の人はわかってくれると信じるよりない。少なくともまともな内容のメールは送信されていないから、相手も詐称メールであるとあきらめているはずだ。
ではこのような迷惑メールと、本当の苦情や相談メールとをどうやって見分けるかであるが、もう見分ける必要はない。基本的にこれまでやり取りのないアドレスから来たメールは無視することが一番である。それでも自分で確かめたいのであれば、まず絶対に返信はせずに、件名や送信アドレスを検索サイトで探してみればよい。同じ被害を受けた人たちの記事がきっと見つかるはずだ。
社内メールにそうしたメールが入ってきたときは、社内のOA管理者に必ず相談してほしい。社員一人が不用意に返信をしたために社内ドメインがスパムリストに登録されれば、本人だけでなく社員すべて会社全体にスパムメールが送信されて多大な迷惑をかけることになる。それが本当に新たな取引先の問い合わせであればそれなりにしっかり文書が書かれているものである。たまに署名を忘れる例もあるようだが、初コンタクトの会社への問い合わせで署名を忘れるような社員がいる会社はスパムでなくとも取引しない方が良い。
どちら様かはこっちが聞きたい。
良心を利用した悪質勧誘メール(実際に当サイトへ着信)↓
|
|
送信者: 坂本あずさ <happy_azusatan@yahoo.co.jp>
受信日時: Mon, 4 Apr 2005 15:33:05 +0900
宛先: yamome@excite.co.jp
Cc:
件名: メールが届きました。
最近あなたからのメールをよく受信するんですが、どちら様ですか?
はじめは迷惑メールか何かかと思ってたんですが、そんなにおかしな内容じゃなかったので
とりあえず返信して見ました。私のアドレスに見覚えはございますでしょうか?
ご連絡頂ければ幸いです。
|
|
|
|
|
■EDIの罪悪(2005.3.13)
EDIをご存知だろうか。企業のOA管理をやっている方であれば、導入で少なからずもめた経験があるのではないだろうか。
EDI(Electronic Data Interchange)は電子データ交換と訳され、データのやりとりに発生する無駄をなくしたシステムである。これを企業活動では、定期的継続的に決まった客先と取引する場合に、その都度発注内容を電話やFAXで受け取るのでなく、直接注文主に注文データを送信してもらい、それをそのまま製造、発注データとして処理することに利用する。従来までの注文内容を人が聞いたり書いたりしたものを、あらためてシステムに打ち込んで処理するのと異なり、効率や発注スピードのアップ、発注間違いなどのトラブルを防ぐことができる。
しかしこのシステムは共通した規格が全くない。管理人の会社の場合は注文をEDIで受ける立場であるが、注文主ごとにEDIシステムが異なる。インターネットを利用するもの、専用線へ接続させるもの、アナログ回線に接続させるもの、IPSECを利用して接続するものなど、注文主ごとにばらばらである。注文主は「注文が入れてあるから見に来い」と言わんばかりに注文を引き出すための様々な処理を強要する。様々なソフトウェアを導入させられ、ネットワークの設定変更も個別に行なわなければならないから、機器の統一性や安定稼動などあったものではない。
しかし我々システム管理者側は、導入したくもないこれらシステムを導入しなければならない。導入しないと取引ができないから、注文主ばかりか利用者側からも「どうにかしろ」と迫られる。前述のように社内標準と大きくかけ離れてしまったシステム設定が原因で、機器も不安定にもなるから利用者側からもクレームも出る。やむなく対応すればオペレータには「わたし忙しいんですけど!」と溜め口を吐かれる。誠に馬鹿らしい。
これまで社内ネットワークを守るために、吟味しながら導入してきた機器やネットワークが、注文主たちの勝手なできそこないシステムで台無しである。注文する側とされる側という主従関係を、これまでは営業が我慢してきたわけだが、これを社内に持ち込まれてはネットワークが壊れるばかりか、管理人も病気になる。
|
|
|
|
■架空請求に注意!(2003.12.22)
インターネットショッピングを利用する機会が多い割に、クレジットカードの明細をあまり見ない人はすぐに明細を確認した方が良い。
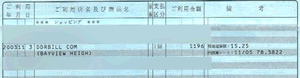
DDRBILL.COM(BAYVIEW HEIGH)という請求がちまたでは騒がれている。どこかのサイトで契約した際にクレジット番号を横流しされたのであろうか。管理人もここからの請求がクレジットカード支払い明細に突如出現した。身に覚えのない請求に支払う義務はないから、クレジット会社に仲介してもらえば解約できるが、少額だし面倒くさいし等の理由で放っておく例が多いそうだ。請求すれば金を払ってくれるだろうというふざけた業者はインターネットはもちろん、資本社会の取引市場に存在してはならないし、恐れや面倒くささがあろうとも利用者はこれに屈してはならない。これを恐れてクレジットカード決済をする人が少なくなれば、インターネットそのものの発展にも大きな障害となる。すでにスパムメールという一部の悪質業者の行為により、電子メールの利便性がスポイルされてしまった。そして電子メールと並んでインターネットの持ち味であるはずのクレジット決済までもが、こうした一部の不届き者の行為により自由を奪われつつある事実は、残念を通り越して腹立たしい。
ともかく自分は大丈夫とは思わず、一度でもインターネット決済を利用した方は明細を確認し、もし該当する場合は一日でも早くクレジット会社へ連絡してほしい。
|
|
|
|
■保守方針の転換(2003.11.15)
先日社内ネットワークが猛烈なスピードで凶悪なウィルスに汚染されました。どこからどのように感染したのか全く不明であり、ある日ある時刻に複数の事業場で一斉に感染拡大の報告のみ残っています。これらが狙うWindowsの脆弱性を常にWindowsUpDateで塞いでおけば被害は最小限に防げたとは思います。ですが、うちではユーザにアプリケーションやドライバを勝手にインストールさせないためにコンピュータのアカウントに管理者権限を与えていませんでした。当然WindowsUpDateもできないわけで、感染を許しました。これまで感染しなかったのが奇跡に近いと言えるかもしれません。
さて、これを機に今後の保守方針を変えていかねばなりません。二度と同じ過ちを繰り返さないためには、管理者権限のない何も変更できないコンピュータではなく、常に修正パッチやWindowsUpDateが行なえやすいコンピュータを利用者へ配布することが第一になります。しかしこれは利用者にいたずらにコンピュータを変更する自由を与えることとなり、アプリケーションやドライバの勝手なインストールによる機器管理の崩壊、それによる不具合の続出で保守保全グループの手が回らなくなることが予想されます。これら保守管理を危うくする行為に対して、これからは利用者に対して「できなくする」のでなく、「できるけどさせない」、つまり社内のコンピュータの利用基準を「運用」で徹底する。会社のコンピュータは家庭のパソコンとは違って、業務を遂行するための生産装置であることを判らせたいと思います。生産装置の内容を変えて操業を停めることと何ら変わらない行為であることをわからせねばなりません。コンピュータを自由に使わせても管理はできるとする者、業務優先を謳ってソフトの逐次インストールを主張する者、まして利用者全員までも敵にまわしかねない今回の決断を、管理人はたとえ今の部署を追われることになろうとも、主張を続けるつもりです。
|
|
|
|
■メディアコピーの良識について(2003.9.23)
大容量メディアに限らないが、コピーに対する法律は守っていただきたい。ファイルの容量がみるみる増え、すでにCD-RはおろかDVDでの記録が常識になりつつあるが、コピーに対する常識は依然低い。個人データのコピーは作成者本人が扱う限り自由であるが、市販のビデオなどのDVDコピーはコピー操作を行なうこと自体が法律違反である。この点は購入者本人だけで利用する範囲で複製を許可する市販音楽CDとは異なる。
コンピュータ雑誌でもよくDVDの特集がある。驚くべきことは、合法のデータ用DVDのコピー操作に加えて、ビデオDVDのプロテクトはずしのソフトウェア紹介が書かれている場合がある点だ。「法律に触れるから行わないように...」とわずかに書き加えれば何を書いてもいいというものではない。
日本国内では試すこと自体犯罪であるから、これら雑誌の無責任な記事に惑わされることなく、間違ってもやってみようなんて気を起こさないで欲しい。これは犯罪なのだから。
|
|
|
|
■ダジャレショップ(2003.1.31)
おもしろいお店の紹介を。パソコンの周辺機器(そうでないものもある)メーカーだが、その商品の命名がとてもおもしろい。みなダジャレだ。「キリーポッター」、「エアフォースファン」、
極め付きはパソコンの静音キット「駆動静か」だあ!
イーレッツ株式会社
http://www.e-lets.co.jp/
|
|
|
|
■ゲリラ広告反対!(2002.11.13)
エキサイト(http://www.excite.co.jp)にアクセスすると、思っていたものと全く違う画面が表示される。最近流行のフラッシュ何とかだか知らないが、強制的に全面広告を見せられたあとはじめて、エキサイトの画面が開く。恐らく2秒程度のことだろうが、見たくない者にとってこんなにうっとおしいものはない。当サイトのようにこっそり入れるならともかく(^^;これでも管理人は胸が痛む)、大手のポータルサイトが全面広告ときたものだ。他にインフォシークでもやっているようだ。エキサイトは「ホーム画面(いつもインターネットエクスプローラを開いたら最初に出る画面)にしてもらうにはどうしたらよいか」なるアンケートを以前、無料メールを利用する管理人に送ってきた。何を言うか!こんなうるさいページをホームにできるか!当時世間で評判の坊主頭のサッカー選手の顔が円を描いて並ぶ広告が何度も何度も表示されることに不快である旨記したが、相変わらずこの強制広告は続き、先日は某自動車会社の宣伝がうるさく表示された。ちなみに今はインターネットで決済できる銀行の宣伝が出てくる。これが嫌だというのは恐らく少数意見だったのだろうか。
先日、エキサイトにこのことを抗議したところ返答があった。以下全文。「ご理解のある企業様」というのが理解できない。これだけ乱暴な広告を出さなければスポンサーにならない企業のどこが「ご理解のある企業様」なのか。見る側は理解してもらえないのか。スポンサーの顔色うかがうあまり運営方針を変えたメディアがどれだけあったことか。数ある苦情メールの中からただちに返答をくれたその姿勢だけは評価したい。それだけに惜しい。
差出人: "Excite
Customer Support" <mailsupport@excite.co.jp> アドレスを保存
ジャンクメールをレポート
メールを印刷
ヘッダを表示
日付: Tue,
5 Nov 2002 19:06:44 +0900
宛先: <mailsupport@excite.co.jp>
件名: エキサイトカスタマーサポートメッセージ:AD
--------------------------------------------------------------------------------日頃弊社サービスをご利用頂きまして、誠にありがとうございます。
エキサイトでは現在、全面フラッシュ広告を掲載しております。本広告
プログラムはクッキーにより1つのコンピュータに対する最大表示回数
を定めております。規定回数の配信をすると以後、同一の広告は表示さ
れなくなります。さらに画面端の[Skip To Excite]のリンクより広告ページを
スキップさせることもできます。
ご指摘いただいた内容については担当に報告のうえ、今後のサービス展
開の参考にさせていただきます。
エキサイトでは、ユーザーの皆様にご満足のいただけるサービスを日々
模索し、より良いサービスを提供していきたいと考えております。その
ニーズにお応えするためにも、皆様の忌憚なきご意見は大変貴重です。
これからも多岐にわたる新たな試みに取り組む中では、必ずしも全ての
お客様にご満足いただけないこともあるかと存じますが、皆様のご意見
を伺いながら、よりご満足いただけるサービスを提供していきたいと考
えております。
また、エキサイトではサービス運営の費用の多くを、インターネットに
ご理解のある企業様からの広告料で賄っております。何卒ご理解の上、
引き続きエキサイトをご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
エキサイト株式会社
http://www.excite.co.jp/
**************************************************
この電子メールは原則的にテキスト形式を用いて送信されております。
また、本電子メールは送信専用となっております。
本E-Mailアドレスへのご質問はお受けできませんので、予めご了承ください。
再度ご質問あるいはご回答のある場合は、お手数ですが、
下記URLよりご質問内容を送信していただけますようお願い致します。
「ご意見ご感想」:http://www.excite.co.jp/help/info?hp=7
**************************************************
|
|
|
|
■広告入れました(2002.8.18)
広告が入ってやかましいとの意見もあろうかと思います。このところのアクセス数の増加と共に広告掲載の申し出がメールされてくるようになりました。大手企業のものから、いかがわしいものまで様々ですが、比較的バナーのおとなしい一社を選んで入れてみました。バナー広告を入れた目的は、どの程度サイドビジネスとして使えるか試すものですので、1年ほどで元に戻すつもりです。
ちなみに広告依頼メールが激増したのは、Googleに登録完了してからでした。Googleの内容が他のポータルサイトでも広く利用されているせいでしょうか。ホームページの来訪者を増やそうと思う方は、どこよりも先にGoogleへの登録をお勧めします。接続数アップの近道です!
|
|
|
|
■掲示板の記載に注意(2002.6.17)
先日、何げなく知人の名前を検索サイトに入力してみたら、ヒットした。もちろんそれはあってよいことだが、メールアドレスまでもが表示されてしまっている。
その人が買い物をした店にお礼をしようと、その店のホームページにある掲示板に礼状を書いたものだが、検索サイトの対象が掲示板の中まで拾ってしまっている。店側が宣伝のために掲示板の内容も含めたものであろうが、掲示板がメールアドレスを表に出す粗末な構成のものであったため、検索サイトで紹介されてしまった。掲示板を自作する場合はメールアドレスは記入しない方式にするか、または階層を1段下にする(たとえば名前をクリックするとメールアドレスにたどりつく)などしないと、せっかく返事をくれた閲覧者に迷惑をかけてしまう。もちろん検索サイトの対象に掲示板のアドレスを加えるなどもってのほかである。当サイトもその辺を考慮しつつ、掲示板を準備中である。
|
|
|
|
■プリンターの裏紙使用(2001.10.28)
裏紙といっても通じない方もいるかも。プリンターの用紙代を節約するため、使用済みの用紙を裏返して使用する事業所があります。
一枚の紙を2度使用するわけで、確かにコストは半分。しかし2〜3年にわたりこうした使い方をすると、紙から剥離したトナー粉がプリンター内部で変質固化し、ドラムや回転部がこれにより破損します。印刷方向すら確認せずともかく出してみるというルーズな印刷が失敗した裏紙を増やし、裏紙がたくさんあるから試し刷りに使用するという悪循環です。結果、数万円の修理代を何度も支払うはめになりますが、壊れるプリンターが悪いと反省しない人たち。通常、メールサーバと言えば最低構成でも20〜30万円という価格設定がほとんどである中、スパムメール対策などそれらと同等の実用性堅牢性を持ちながら、価格はわずか¥3,000です。上記ページに記載の場所へ送金するか、Vectorなどのオンラインショップでも購入が可能です。購入前の試用動作の場合、メールユーザが2アカウントに限定される以外は機能制限なし。動作確認の後購入を決められます。
これからは管理人へのメールはwebmaster@yamome.comでお願いします。もちろんメールリンクもこれに変更してありますので、ご利用ください。 |
|
|
|
■ファイルが消えた?(2000.10.30)
と言っても、別にウィルスのいたずらではないのですが、サーバ上のファイルが消えたので復旧してほしいとの連絡がありました。ファイルが消えたからにはそれなりのことをしたと思うのですが、誰も消した覚えはない,だからサーバのバックアップテープからデータを戻してほしいとのこと。
いつもであれば、消えた原因を技術的に書くところですが、ここではOA機器利用のマナーについて書いてみます。
皆さんの会社でも、ファイルを過って消してしまったという事件(人為事故)はよくあると思いますが、そのときどうするでしょうか。まず消してしまった原因を確認し、再発防止策を当事者に徹底させると思います。もし本人が覚えがないとのことであれば、どうして消えたのか誰が消したのか調査をするはずです。しかしこの事業場では消えた(消したではなく消えたというのです!)から戻してほしいと言うだけで、自分達で調査をしようとしません。そのくせ、戻らないならあきらめても良いと言うのだから、ばかにしているとしか思えない。
OAを管理している我々の負担を業務と思わない、自分たちに責任はないと思っているこの人たちに、インターネットだ、ITだと「おもちゃ」を買い与えるのはどうしたものでしょうか。
|
|
|
|
■在宅勤務(2001.1.12)
この度、うちの会社でも在宅勤務が実施されました。今度その方のご自宅へお邪魔して、会社のネットワークとの接続環境を実現する予定です。
これまでOA機器の管理というと社内に限られており、例外として以下の場合がありました。
(1)営業などで社外(移動中、他社内)で利用。
(2)業務で使用することを前提に、機器を自宅で使用するため貸し出す。
(3)関連会社出向社員に貸し出す。
いずれも機器が故障したり、盗難にあった場合の対応(保証、費用)が難しいのが特徴です。特に(2)の場合で、盗難に遭うと、双方共に嫌な思いをすることになります。もしこのような使用例を管理している方は、機器の盗難保証やリース規定に目を通しておくことをお勧めします。
今回の例は機器や接続装置はすべて個人で用意したものを使用するため、上記のような問題はないのですが、保守管理方法の問題があります。保守業者がどこまで対応できるか(平たく言えば電話一本で個人の自宅まで行くのか)という問題です。保守業者は一般的に対応守備範囲が決まっており、決まった場所(事業場)しか行かないことになってます。今後増えてくると思われるこの業務形態に合わせてその都度、規約を改定することになるのでしょうか。
SOHOの本格的な実施に向けて、保守方法の見直しが必要かもしれません。
|
|
|
|
|
|
|